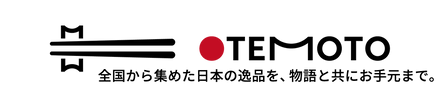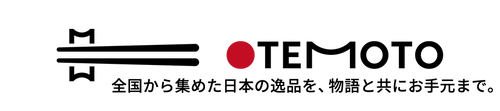「みすゞ飴」の存在が文化そのもの。 伝統を守りながら進化する飯島商店{作り手インタビュー}
投稿日: 投稿者:OTEMOTOSTAFF

信州・上田の果実菓子『みすゞ飴』。100年を超えて愛される理由
信州・上田の伝統銘菓「みすゞ飴」。
カラフルで素朴な見た目がレトロで“映える”。国産果実・無添加・手作りで、今っぽい。
そんな「みすゞ飴」が100年を超えて愛される理由を探りに、OTEMOTOは飯島商店さんをお尋ねしました。

飯島商店の皆さんは折り目正しく、おしとやか。ここで働く方々と触れ合うと、「ああ、この人たちが『みすゞ飴』を作っているんだ。どうりでやさしい味がするわけだ」と、納得がいくというもの。
一方で社長は、豪快さと繊細さ、頑固さと柔軟さが同居する、チャーミングな人物です。
今回はそんな飯島社長に、飯島商店の歴史と現在、そして未来についてお聞きしました。
株式会社飯島商店
代表者:代表取締役社長 飯島新一郎
所在地:長野県上田市中央1-1-21
事業内容:和菓子、洋菓子、生菓子の製造・販売
創業:1816年(文化13年) 屋号「油屋」で創業
飯島商店で働く「ひと」
「みすゞ飴が好き」な人たちがつくる美味しさ
── 創業は何年ですか?
株式会社飯島商店としての創業は大正8年、1910年です。
2019年、台風19号があった年に前社長が急逝し、私が代表を引き継ぎました。急な出来事でしたね。
── 従業員は何人いらっしゃいますか?
約110名です。地元・長野県の方が非常に多いです。中には県外の方もいますが。
販売は30代が多いです。
製造は平均年齢50歳を超えています。ベテランが多いですね。
毎年、数人ですが新人を迎え入れています。
── どのような方が多いですか?
みすゞ飴が好きな人が多いです。「みすゞ飴がきらい」という人は少ないと思います(笑)。
自己主張が激しい人はあまりいないですね。みんな、どちらかというと大人しいです。
── 働き方の特徴はありますか?
うーん、どうだろう? 残業はあまりないですよ。世間が「働き方改革」と言い出す前からそうでした。
私も以前は別の企業に勤めていましたけど、「定時のベルダッシュ」をする会社は初めて見ました。びっくりしたのを覚えています(笑)。

「みすゞ飴」のなりたち
地元・長野県へのこだわり
── 大正8年の設立当時から「みすゞ飴」があったのですか?
はい、明治の末あたりに「翁飴(おきなあめ)」として売り出しています。
翁飴は『高橋』さんという有名な会社がありますが(高橋孫左衛門商店、新潟県)、そちらが作っていたものを基に、果汁を加えて新しく作ったのが「みすゞ飴」です。

私たちはセロハン包装のみすゞ飴を通称「小飴」、和紙包装のみすゞ飴を「新型」と呼んでいます。
「新型」があるということは、つまり「旧型」があるんですよ。
「旧型みすゞ飴」は翁飴の形でした。平べったくて正方形で、ひし餅のような。
今はオブラートを巻いていますが、もともとは上新粉をまぶしていました。
これが「みすゞ飴」の原型です。まったくもって「翁飴」だった訳です。
「旧型」はサイズが大きかったんですよ。「一口で食べられるものを作ろう」と作ったのが、一口サイズの「新型みすゞ飴」です。
── いつから「みすゞ飴」になったのですか?
明治の末くらいに「翁飴」という名前で販売していたみすゞ飴の原型を、大正時代に「みすゞ飴」という名前に変更したようです。
み薦刈る信濃の真弓吾が引かば
うま人さびて否と言はむかも
万葉集の歌です。
「みすゞ刈る」というのが信濃国の枕詞で、「みすゞ飴」はそこからの名付けです。「あをによし」が奈良県の枕詞のように、ですね。
この枕詞は、江戸時代の国文学者・賀茂真淵が「みすず刈る」と読んだものです。ですが、昭和の時代に「みすず刈る」ではなく、「みこも刈る」が正しい読み方、というのが通説になったんです。
でも、いい時代に名付けたものだと思います。誰も「みこも」なんて言いませんからね。
「みすず書房」ですし、「金子みすゞ」ですし。賀茂真淵はいい誤読をしてくれました。

飯島商店の信念
「変わらない」ために「変える」こと
── 創業から今に至るまで、変わらず大切にされていることは何ですか?
なかなか難しい質問ですね。創業時と今とでは社風も変わっていますので。
社長の性格によるところが大きいですが、二代目の飯島春三の代、私の祖父の代に当たりますが、そこからは保守的な経営に移行しています。
なので一概には言えないんですが、ただ一つ言えるのは、「地元のものを大切にする」というところです。
信濃国の枕詞「みすゞ刈る」をとって「みすゞ飴」としていることから分かるように、「地産地消」がベースにあります。まあ、当時は「地産地消」なんて考えはなかったんですが。
長野県の「寒天」と「果物」、自社製の「水飴」。これらを使って、長野県ならではのお菓子を作りたい、と。
今は長野県だけではなく、三宝柑なんかは和歌山県産のものを使用していますが、いずれにしても「近場の、顔が見える範囲で、信頼できる原料を使ってものづくりをする」── このフィロソフィーはずっと変わっていません。
とはいえ、創業者の飯島新三郎は非常にやり手でしたから、他の地域のお土産を作ったりしていたみたいなんですがね。広島の「もみじ飴」とかって(笑)。
今は、OEMはやっていません。

── 社長の代で変えたことはありますか?
いっぱいあるんじゃないかな!先代は自動ドアが大嫌いだったけど、自動ドアをつけたりね(笑)。
先代は「自動ドアなんてとんでもない!」という人でしたが、分店は今は自動ドアになっています。見たら卒倒するんじゃないかな(笑)。
先代、先々代の社長だったら、今回のYouTuberコラボもなかったでしょう。
保守的で、「外の人間を中に入れるなんてとんでもない」、そういう考えでしたから。

YouTuberロシアン佐藤とコラボした「みすゞ飴」
これまでの根本にあったのは、「説明しなくても、わかってくれる人に選んでもらえればいい」という考えなんです。それはそれでいいんですよ? でも私は、「それでいいのかな?」と思います。
この時代において「手づくり」を守っていくことは、やはり容易ではないんです。
お客様には、やっぱり正しい選択をしていただきたい。
「手づくり」を見せていかないと、価値をお伝えできない。お客様に正しいチョイスをしていただけない。
正しいチョイスをしていただくためには、情報が必要。
その情報を提供するのが販売の仕事だし、「人がいる意味」じゃないの。と思っています。
だから、なるべくオープンにしていきたい。
これは完全に、私の想いですね。
それで、いろいろな広報をやっているところです。なかなかうまくいかないですが。
うまくやりたいな、そう思っています。
── これだけは変えたくない!ということはありますか?
基本的に何も変えたくないですよ(笑)。

新入社員が入ってきた時は、必ず「この二つだよ」と言っています。
一つは、「みすゞ飴だよ」と。
長野県の「みすゞ飴」は絶対に守らにゃならん。「みすゞ飴」の製造と販売を疎かにすることは有り得ないこと。長野県に対して申し訳がたたないし、長野県でやっている存在価値を失うことになる。
「絶対に守るよ」と、宣言しています。
もう一つは、「文化財を守ること」。
哀しいかな、現在の上田駅は文化の香りがするものが、何もない。
飯島商店の建物がなくなってしまうと、いよいよ上田は総崩れになってしまう。
だから、これをきちんと守る。それが、我々が「上田にいる意味」だよ、と。
一次加工から最終製品に行き着くまで、一気通貫で自社製造。
ここが崩れると、みすゞ飴も文化財も守れないよ。
この二つを守るために打てる手は、何でも打ちましょう。
そう伝えています。

飯島商店上田本店 国指定登録有形文化財
飯島社長の苦悩
ブランドの「怖さ」と「有り難さ」
── 迷ったこと、苦しんだことはありますか?
迷って苦しんでばっかりですよ!(笑)
まずは毎年の値上げです。
手づくりでやっている以上、「ひと」がいなくては成立しません。
けれども、この程度の売上の会社で110人以上の従業員を雇っているのは、人数が多すぎるんです。
多すぎるんですけど、こだわりや品質のためには、「ひと」が必要なんです。
なかなか厳しいです。

何が厳しいかと言うと、どんどん人件費が上がっていく訳ですから、お客様へのお願いをしなくてはいけなくなります。
つまり、「値上げ」です。
機械化している他社以上に、お客様へ値上げのご迷惑をおかけしているというのが現実です。
これをご説明して、「嫌だ!」というお客様はいないのですけど、納得して買っていただけるかというと、それはまた別なんですよね。
正直、怖いです。
いつか見放されて、買ってただけなくなるのではないか、と。
従業員が110名以上いる訳ですが、明日の給料が払えるだろうか、って。

この恐怖感があるならば、変えていかなくてはいけないですよね。
ただ値上げするのではなく、ご納得いただけるように、高品質化させる。
あるいは、パッケージなどのデザインの部分で魅力を増す。
そういった取り組みを、とにかくどんどんやっていかないと、非常に危ないぞ、と。
どうしたらいいのかなって。日夜考えています。
とにかく何でも、打てる手は全部打ちたい。
打たなくていいなら、打たないんですけどね(笑)。
楽しくて変えてることは、ほとんどないです(笑)。
変えなくちゃいけないから変えています。
でも悲壮感たっぷりでやっていたら人生つまらないので、無理矢理でも「楽しい」と思ってやっています(笑)。
店舗にいらしていただければ、「おや、なんかいろいろ変わったな」とお感じいただけることもあるかと思うのですが、それが試行錯誤の証です。
──「みすゞ飴」ブランドを背負っていらっしゃるんですね
ん〜、そうですね。
でも、ありがたいことです。
ここまでのブランドは、なかなか得がたいものです。非常に恵まれています。
「みすゞ飴がなんかやる」ってなったら、「あ〜、”みすゞ飴が”そんなことやるんだ」ってなりますからね。アドバンテージです。

「みすゞ飴」を守る価値
みすゞ飴自体が”文化”だから
── 最後の質問です。「みすゞ飴」という商品を通して、次の世代へどういう価値を届けたいですか?
ん? 難しい質問ですね。
「みすゞ飴」自体が価値だと思ってやっているので、考えたこともないです。
「みすゞ飴」があること自体が、一つの文化的価値だと思っていますよ。
長野県のトップブランドとして、100年以上の歴史があります。
100年以上、手づくりを続けています。
それ自体に、非常に価値があると思っています。

関連商品
関連動画
関連記事
- 古くて、新しい。100年つづく信州・上田の果実菓子『みすゞ飴』を、あなたに届けたい
- 「みすゞ飴」の存在が、文化そのもの。 伝統を守りながら進化する飯島商店{生産者インタビュー}
- 【信州上田】女子旅で行きたい!おすすめグルメスポット7選
編集後記
地元の、歴史あるブランドを背負う飯島社長の胸中に触れることができたような気がしています。
それにしても、最後の質問は社長にとって拍子抜けだったようです。
「みすゞ飴」自体に文化的価値がある。
めちゃくちゃ格好良いですよね。
私の頭の中では『プロジェクトX』風に再生されています。
飯島社長、ありがとうございました。
 |
取材・写真・文章:中川彩野、長野県岡谷市出身 |
OTEMOTOプロジェクトは、作る人と食べる人を繋ぐ橋渡し役として、作り手のストーリー、作り手が愛情を込めて作った食べ物のストーリーを、割愛せず丁寧に伝えていきます。
今回の作り手インタビューは、株式会社飯島商店 代表取締役社長 飯島新一郎さんにご登場いただきました。
今後のインタビューもお楽しみに。